「扶養」と聞いて、皆さんは何を思いつきますか?
健康保険料や配偶者の国民年金と言った、保険料がかからない?
所得税や住民税と言った税金が安くなる?
そう、扶養には社会保険上と税法上の2種類があって、それぞれ違った特徴があります。
特に年末になると、配偶者の扶養内に収入を抑えようと、パートの勤務調整をする人が増えますが、このそれぞれ扶養の特徴を勘違いしてしまうと、大変なことになってしまうかもしれません。
今回はそんな2種類の扶養について解説していきます。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、簡単に言うと健康保険の扶養のことです。
一般的な家庭を例にすると、まずAさんがいます。
このAさんがお勤め先で社会保険に加入します。
そうするとAさんは社会保険(厚生年金保険と健康保険)の被保険者になります。
で、このAさんには配偶者とお子さんがいるとしましょう。
健康保険は日本では国民皆保険と言われていて、生まれてから死ぬまで、必ず加入しなければならないとされていますので、配偶者やお子さんも健康保険に加入しなければいけません。
ただ、保険なので当然、保険料がかかります。
家族全員がそれぞれで保険に加入して保険料を支払っていたら、支出が増えてしまいますよね。
そこで、すでにお勤め先で社会保険の被保険者となっているAさんに扶養してもらうことで、保険料が安くなったり、全くがかからずに、Aさんが加入している健康保険に加入することができる、と言うのが社会保険上の扶養です。
健康保険証を見ていただくと、Aさんの保険証には「被保険者」、配偶者やお子さんの保険証には「被扶養者」と記載されているかと思います。
また配偶者の場合は、Aさんの扶養となることで国民年金保険料についても免除されます。
社会保険上の扶養とは、扶養される人の保険料がお得になると言うことなんですね。
社会保険上の扶養の範囲
扶養には一定の条件があり、その一つが扶養者と被扶養者の収入です。
扶養者、扶養する側なので、今回の例ですとAさんですね。
それから被扶養者、扶養される側なので、配偶者やお子さんになります。
社会保険上の扶養とする場合、まずは被扶養者のこの先一年間の収入見込みが130万円(60歳以上や障害をお持ちの方の場合は180万円)未満である必要があります。
ポイントは「この先一年間の収入見込み」というところと、ここで言う収入とは、給与収入、年金収入はもちろん、失業給付や傷病手当金といった給付金なども含みます。
なので、例えばAさんの配偶者が、今までご自身で勤務先の社会保険に加入していたけど、お仕事を辞めた、といった場合、お仕事を辞めているわけですから「この先一年間の収入見込み」は0になりますよね。
その場合は、勤務先を退職後、すぐにAさんの扶養になることができます。
ただし退職後、失業給付を受給する場合、「この先一年間の収入見込み」が発生するわけですから、年収130万円未満という扶養の条件を満たさないと、Aさんの扶養にはなれません。
日額いくらまでなら扶養対象になるかというと、
失業給付はひと月を30日として考えますので、1年は30日×12ヶ月で360日。
年収130万円÷360日≒3,611円となりますので、支給日額が3,611円以下なら、扶養対象となるということです。
他にも扶養の条件として、被扶養者の収入が扶養者の収入の½以下であること、というのがあるんですが、こちらはあくまで原則的な条件となりますので、収入の条件に関しては、年収130万円未満、という事を抑えておくようにしてください。
税法上の扶養
では次に税法上の扶養について。
先程の社会保険上の扶養は、扶養される人の保険料が安くなったり、免除されてお得ですよ、と言うお話をしましたが、税法上の扶養は扶養する人の所得税や住民税と言った税金が安くなると言うメリットがあります。
親族を税法上の扶養対象とするには、毎年、扶養控除等申告書に扶養対象者の氏名や生年月日、所得額などを明記して、扶養する人、今回の場合はAさんが勤務先に提出する必要があります。
税法上の扶養の範囲
社会保険上の扶養と同様、税法上の扶養にも収入の条件があります。
ただし社会保険上の扶養の条件が「この先一年間の収入見込み」であるのに対し、税法上の扶養は毎年12/31時点での1月から12月の実収入になります。
税法上の扶養とする場合、被扶養者の収入が給与収入であれば103万円以下、年金収入の場合は65歳未満は108万円、65歳以上は158万円以下である必要があります。
ここで言う収入とは課税収入のことをいいますので、例えば非課税通勤費、失業給付や傷病手当金といった給付金、また年金ですと遺族年金や障害年金などは非課税となりますので含みません。
ただし税法上の扶養というのは、本来は収入ではなく所得で判断しなければいけないんですね。
では所得とは何なのか。
ここから少しお話が難しくなりますよ。
所得、というのは収入から費用を引いたものを言います。
この費用がいくらなのかは、法律で定められています。
- 給与収入なら55万円。
- 年金収入なら65歳未満は60万円(65歳以上は110万円)
※年齢はその年の12/31時点での年齢
税法上の扶養は、所得額が48万円以下の親族が対象となるので、例えば65歳以上の親を扶養とする場合、給与収入60万円、年金収入が150万円だったら、給与所得は60-55=5万円、年金所得(雑所得)は150-110=40万円。
合計所得額は45万円となるので、扶養対象となります。
もし給与収入が65万円であったら、合計所得額が50万円となり、48万円を超えてしまうので、扶養対象とはなりません。
※配偶者に関しては所得額48万円超でも、所得税法上の扶養となれる配偶者特別控除という優遇措置があります。
まとめ
扶養には2種類あるというお話をしました。
社会保険上の扶養は、扶養される人の保険料がお得に、税法上の扶養は扶養する人の税金がお得になる、という内容でしたね。
扶養にはそれぞれ一定の条件あり、特に収入条件には注意が必要です。
法改正により条件が変わることもありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
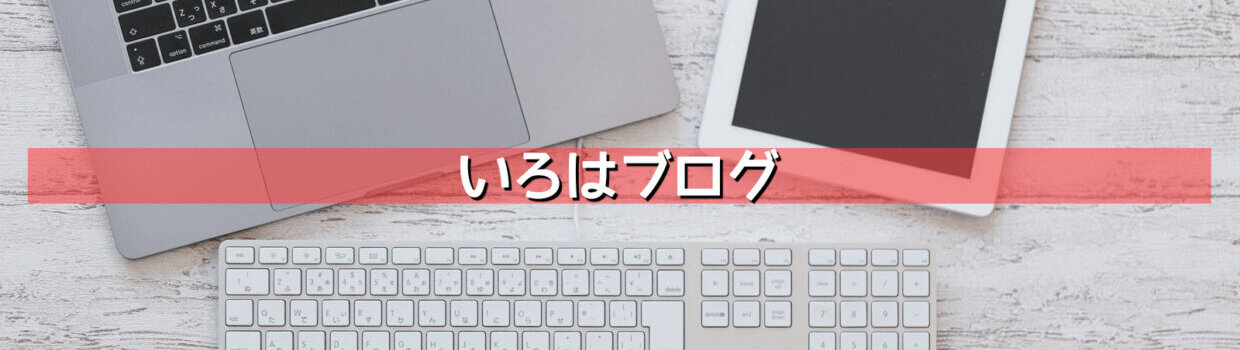


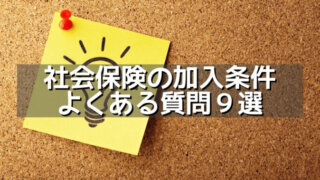




コメント