労働基準法、健康保険法、育児介護休業法…
労働者にかかわる法律は数多くありますが、毎年必ず何かしらの法改正があります。
法律が変われば当然、様々な制度も変わります。
今回は今年、2022年に改正予定の法律と制度について解説していきます。
マルチジョブホルダー制度の新設(1月)

こちらは雇用保険法の改正となります。
現在、雇用保険の加入要件は、
- 週の労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用の見込みがある事
とされています。
しかし、最近はダブルワークをされている方も多くいますが、1つの事業所で週10時間、もう1つの事業所で週15時間といった働き方をしている場合、どちらの事業所でも雇用保険には加入できないですよね。
それが1月の法改正により65歳以上の方の場合、2つの事業所の労働時間を合算して、週20時間以上であれば雇用保険に加入することができます。
あくまで任意ですので強制ではありませんが、手続き自体は労働者本人がしなければならないので、そちらだけ注意が必要です。
傷病手当金制度の変更(1月)

こちらは健康保険法の改正となります。
傷病手当金は、私傷病により仕事を休んで賃金の支払いを受けなかった場合に支給される給付金制度となっていますが、支給期間は支給開始日から1年6ヶ月となっています。
ただ病気の場合、一旦、治療が終わって復職しても、再発してしまうことってありますよね。
今までは復職期間についてこの1年6ヶ月に含まれていたんですが、1月の法改正により復職期間については支給期間の1年6ヶ月には含まれなくなりました。
要するに、1年6ヶ月分の傷病手当金の受給が可能となり、中・長期的な病気の治療が可能となったわけです。
男性の育児休業制度の改善(4月)

こちらは育児・介護休業法の改正となります。
男性の育児休業制度については、もちろん以前からあったんですが、育児休業は女性の取得率が8割を超えているのに対し、男性の取得率は1割前後となかなか伸びていないのが現状なんですね。
その打開策として4月の法改正で育児休業を取得しやすい職場環境の整備をすることを、事業主の義務とすることにしたんですね。
育児休業と言うのは、あくまで労働者からの申し出により取得が可能なものなので、事業主としては待ちの態勢で良かったんですが、今回の改正により事業主側から労働者に育児休業の取得について働きかけなければならなくなったわけです。
自分からは言いにくいけど、勤務先から働きかけてもらえれば、育児休業が取得しやすくなるかもしれませんね。
パワハラ相談窓口の設置(4月)

こちらはパワハラ防止法の改正となります。
改正自体は2020年6月にされているんですが、大企業に対しての適用だったんですね。
それが4月からは中小企業においても適用されることになります。
パワハラへの対応義務は事業所にありますので、事業所がどういった対応をしなければならないのか、といった具体的な内容は省略しますが、労働者にとって知っていただきたい内容としては、パワハラ相談窓口の設置です。
事業所はパワハラ相談窓口の設置をして、労働者に周知しなければならないとされていますので、今後のお勤め先からの通達には要注目ですね。
在職老齢年金制度の変更(4月)
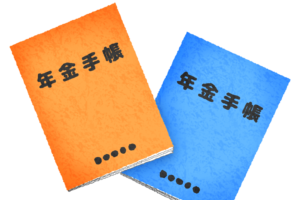
こちらは年金制度改正法の改正となります。
改正ポイントは以下の3つです。
- 受給額の在職定時改定
- 支給停止基準の引き上げ
- 受給開始時期の選択拡大
・受給額の在職定時改定
年金は原則65歳からもらえますが、65歳以上の方が社会保険に加入しながらお勤めをしている場合、今の制度では保険料を毎月納めていても、年金の受給額がすぐに増額されるわけではなかったんですね。
それが4月の法改正により年に1回、今までの加入実績を反映して受給額が増額されるようになります。
要するに、65歳以上で社会保険に加入しながらお勤めをしている方は、毎年、年金の受給額が増えていく、と言うことになります。
・支給停止基準の引き上げ
年金の受給額は企業などでお勤めをしていて、社会保険に加入しながら受給する場合、基準額、ざっくりと言うと受給している年金とお勤め先からの給料を足した金額に応じて、年金の一部、もしくは全額が支給停止になる仕組みがあります。
この基準額が月28万円を超えると年金の一部が支給停止となって、収入が増えるにつれ年金の受給額が減っていくわけですが、4月の法改正により基準額が47万円に引き上げられることになります。
・受給開始時期の選択拡大
年金は原則65歳からもらえますが、65歳よりも早くもらい始めることを繰り上げ、逆に遅くもらい始めることを繰り下げ、と言います。
現在は60歳から70歳の幅で年金の受給開始時期が選べますが、4月の法改正により75歳までの繰り下げが可能となり、受給開始時期の選択肢が「60歳から75歳」に広がることになります。
また繰り上げた場合の受給額の減額率も、繰り上げひと月当たり0.5%だったのが、0.4%となります。
繰り上げた場合の減額が少なくなって、逆に繰り下げ期間が長くなることで受給額は最大で184%にまで増額することが可能となります。
社会保険の適用拡大(10月)
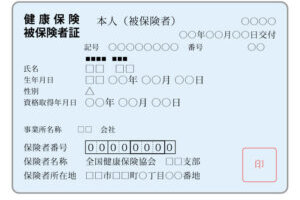
こちらは年金制度改正法の改正となります。
現在、お勤めしている方の社会保険の加入要件は、週30時間以上勤務している方となっていますが、特定適用事業所にお勤めの方の場合は、週20時間以上かつ賃金月額88,000円以上となっています。
特定適用事業所と言うのが何なのかですが、社会保険に加入している従業員数が501人以上いる事業所のことを言いますが、10月の法改正により、特定適用事業所の範囲が変わります。
現在、社会保険に加入している従業員数が「501人以上」となっているのが、「101人以上」となるんですね。
要するに、特定適用事業所となる事業所が増えることになります。
そうなると、今現在はお勤め先が特定適用事業所ではないため、社会保険に加入していないと言う方も、今年の10月からは社会保険に加入しなければならなくなる可能性が出て来るわけです。
特に家族の扶養内で働きたい、と言う方には要注目の改正となりますね。
まとめ
今回は2022年に改正予定の法律と制度について、6つお伝えしました。
なかでも最後にご紹介した社会保険の適用拡大については、注目されている方も多いのではないでしょうか。
法改正は今回ご紹介したような、事前に公表されるものもあれば、突如として改正されるものもあります。
新しい情報を取り入れて、制度をうまく利用していきたいものですね。
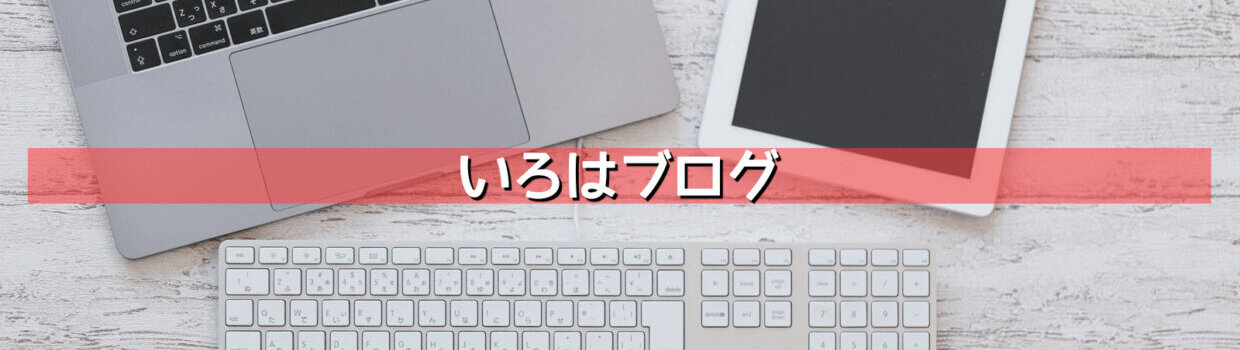


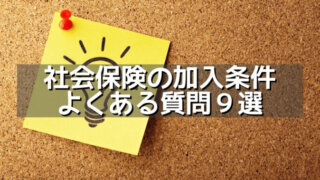




コメント